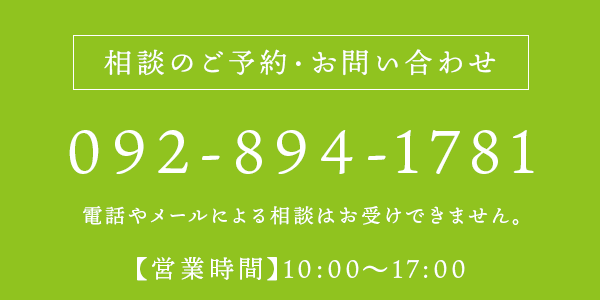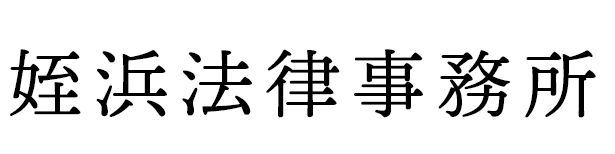| Q.弁護士の専門分野はあるのか? |
| A.これは、相談者からよく聞かれます。 一般民事(貸し金の返還や不動産の明け渡し、交通事故など)や、離婚・相続などの家事事件、起訴後の刑事事件などは、多くの弁護士が取り扱うことの可能な事件です(もちろん、これらの中でも、個人的な信条で離婚事件は取り扱わないとか、刑事事件は取り扱わないという弁護士はいるかもしれません)。 債務整理(自己破産、任意整理、民事再生等)になると、取り扱う弁護士も、取り扱わない弁護士もそれぞれ相当数いるようです。 特殊な分野としては、例えば、著作権問題、国際取引、医療事故、欠陥建築などがあります。これらについては、研究会や、専門の事務所などでの研さんがないと、十分な弁護活動が期待できません。 私は、医療事故を取り扱っていますが、医療事故は、資料の収集方法の習熟だけではなく、協力してもらえる医療関係者との体制などがないと、そもそも勝訴の見込みがどの程度あるのかの判断すら十分にはできませんし、訴訟活動も困難です。 私は、九州山口医療問題研究会という団体に所属し、医療関係者の協力を得ながら医療事故調査や訴訟活動を行っています。この研究会では、2名の弁護士で調査を行い、通常3名の弁護士で訴訟活動を行います。3名は、できるだけベテラン・中堅・若手の組み合わせになるようにして、訴訟活動の質を維持しつつ、医療事故訴訟を担う弁護士を育てる体制がとられています。 残念ながら、適切な訴訟活動がないとして依頼した弁護士を解任し、医療研所属の弁護士に依頼されるケースもたまにではありますが存在しますので、このような特殊な分野に関しては、依頼される前に調査の進め方や、過去の経験等尋ねられた方がよいと思います。 |
| Q.弁護士は、どうして犯罪を犯した悪い人の味方をするのか? |
| A.友人や家族などからも尋ねられることがありますが、法律家以外で、この質問に正確に答えられる方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。 弁護人(刑事裁判で活動を行う弁護士のこと)が被疑者(犯罪を犯したと疑われている人のうち、起訴される前の人)・被告人(同じく起訴された後の人)の弁護をする理由の第一は、その人が、無実であった場合に、間違って刑務所へ送られたり、死刑判決を受けたりしないよう、真相を究明するためです。 十分な証拠がないのに殺人犯人とされ、有罪判決を受けた後、長期間裁判のやり直しを求め続け、再審でようやく汚名をそそいだ人もいます。 きちんと真相究明がなされれば無実が明らかになるのに、思いこみや不十分な訴訟活動で有罪とされ、無実の人を犯人扱いして長期間刑務所に収監したり、あるいは死刑執行がなされたりすることは絶対にあってはならないことです。 実は、刑事裁判というのは、犯人を刑務所に送り込むためのベルトコンベアではなく、無実の人を犯人と認定しないように、慎重に審理を行うことを最大の目的としています。 我が国では、犯人が逮捕されたり、事実上取り調べが始まると、いっせいに報道が集中し、裁判をするまでもなく、その人が犯人であるかのように思われがちですが、それが正しいとは限りません。 長野のサリン事件では、自らも、また奥さんも被害者となった河野さんが、一番最初に警察から犯人と疑われ、捜査が始められました。もちろん、膨大な量の報道も行われました。被疑者段階で弁護人が付きましたが、その時点では、社会的には、河野さんは犯人扱いされていました。 この事件では、比較的早期に弁護人が付き、河野さんの弁解内容が次第に伝えられていきましたが、そうでない場合には、厳しい取り調べに耐えかねて、心ならずも自白してしまう人もいます。 最近の事例では、精神遅滞で、会話すらままならない被疑者から2件の強盗事件の詳細な自白をとって起訴し、その審理中に真犯人が逮捕され、その後の検察官の取り調べで、全く会話が成り立たないことが明らかにされ、2件の強盗について無罪が言い渡された宇都宮事件(宇都宮地裁2005年3月10日判決)や、圧迫と誘導で得られた「共犯者の自白」によって起訴されたものの、全くの人違いであることが審理で明らかにされたため無罪判決が言い渡された大阪地裁所長襲撃事件(大阪地裁2006年3月20日判決)等が有名です。 ですから、報道で、逮捕されたとか起訴されたと書かれていても、頭ごなしに犯人扱いはしないで下さい。自分が間違って逮捕されたり、起訴されたりしたときには、弁護士の活動は頼りになるものだと思います。 刑事裁判においては、弁護人が被疑者、被告人に対して不利益な活動を行うことは禁止されています。 仮に、の話ですが、仮に弁護人が被疑者、被告人の現に行っている無罪主張を信じることができなかったとしても、弁護人は、有罪を前提とする弁護活動を行うことは原則として禁止されています。それは違法な活動として懲戒や損害賠償の対象となります。 また、被疑者、被告人が罪を犯したことを認めている場合であっても、自ら調査して、その人が十分な防御能力がないためにそういっているのではないか、あるいは誰かの身代わりのためにわざとそういっているのではないか、を確認する必要があります。 被疑者、被告人自身が犯罪を認め、資料からそれが間違いないと思われる場合、弁護人の活動の目標は、可能な限り刑罰を軽くしてもらうことになります。 刑事裁判は、被告人に不利な証拠を検察官が可能な限り裁判所に提出し、被告人に有利な証拠を弁護人が可能な限り裁判所に提出し、それを公平中立な第三者である裁判官が判断することによって、真理に到達しようという構造になっています。 つまり、弁護人は、刑事裁判における役割として、徹底的に被告人の主張に沿って、被告人に有利な証拠を集め、法廷に提出し、主張を尽くす必要があり、それが不十分な場合には、正しい判断、公正な判断がなされないのです。 今後行われていく裁判員制度でも、弁護人による十分な弁護活動を保障しないまま迅速に裁判手続きが進められないよう、きちんと見守っていく必要があります。 2007年2月23日に、鹿児島地裁で、公職選挙法違反事件について、12人の全員無罪判決が出されました。 2006年には、富山で、強姦事件の犯人として服役した方が、全くの人違いであったことが分かり、大問題となりました。 最近は、「それでもボクはやってない」という映画が反響を呼んでいます。 日本の刑事裁判が、起訴されればほぼ100%の確率で有罪であり、無実の人が誤って起訴されても、無罪判決を得る可能性がほとんどないことは、たいへん絶望的な状況といわなければなりません。 無実の人を陥れないためのチェックシステムとしての、刑事手続きの意味がなくなってしまうからです。 上に述べた宇都宮事件では、栃木県警内部の検討により、取調官が、手振り・身振りのやりとりの際に、取調官が期待する言葉が出ることをきっかけに、被疑者に迎合されたり、相づちを打たれたりしたことがまとめられています。 つまり、全く経験しない事件の内容について、「いつのことか」「どこだったか」といわれ、当てずっぽうで何回も回答していくと、取調官が、「そうじゃない。」「だいぶ近づいた。」「もうちょっと前だろう。」等と言うので、それに合わせてていきさえすれば、全く身に覚えがないことでも、まるで、自分が犯行を犯したかのように、犯罪事実を説明していくことが出来るということなのです(これは、被疑者の供述というより、取調官の供述というべきです)。 志布志事件の志布志警察署(えん罪大崎事件の担当署でもあります)では、もっと露骨な強制が働いたことが明らかにされています。 このような捜査は、程度の差こそあれ、どこでも行われていることです。 もちろん、大部分の事件では、捜査は適正に行われているものと思いますが、重大事件で、犯人が検挙できないため、警察がなんとか検挙したい場合や、志布志事件のように、政治的な目的がある場合などは、大変危険といえます。 まずは、違法な取り調べをなくすために、志布志事件の徹底解明と再発防止がなされるべきでしょう。 その上で、「違法な取り調べがあった」証拠を被告人に提出させるのではなく、「適法な取り調べだった」証拠を、捜査機関に提出させるようにしなければなりません。 これは、国際的には常識とされていることであり、かつ、我が国の憲法、刑事訴訟法の原則からいって、本来当然のことです。 本来、強制等の疑いが出されたら、適正な捜査を行う義務を負う捜査機関が、適正であった証拠を提出できない限り、強制の疑いだけで自白の証拠能力を否定すべきです。 違法な取り調べをされたのに、捜査機関がしらを切ってしまえば、ほぼ100%有罪判決が決まっている刑事裁判に、あなたは信頼ができますか。 そのような裁判に、裁判員として参加したいですか。 裁判員制度には、本来、取り調べ過程の全面録画化、つまり可視化が不可欠です。 少なくとも、裁判員として参加される方は、「違法な取り調べがあったと被告人が述べても、捜査機関が否定したら、捜査機関を全面的に信用してよい」という、裁判官の意見には、疑問を提示してほしいと思います。 一般市民の健全な感覚を反映させることが、裁判員制度の本来の目的のはずですから。そのような形の改善すら果たせないのであれば、裁判員制度は、膨大な税金と、市民の膨大な負担だけを課し、形式だけ市民参加を果たしたかのような体裁を取り繕った、みせかけの制度になってしまうと思います。 |