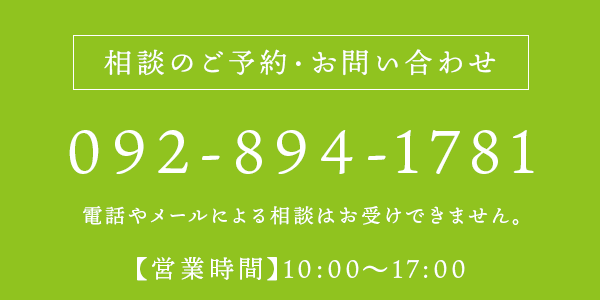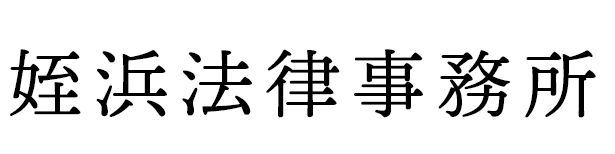医療事故調査、解決のすすめかた
医療機関で、事前の説明と全く異なる結果が生じた場合など、納得のいかない場合で、真相究明をしたいとお考えの方のうち、将来損害賠償請求も考慮されている方は、医療事故を扱う弁護士に相談されることをお勧めします。
医療事故ではないかと疑われるケースでも、やむを得ない結果の場合もあれば、医療機関に責任があると思われる場合もあります。
カルテ等を検討し、医療上の問題の有無、法的責任の有無について調査することが必要です。
調査の結果、問題がないと考えられる場合は、その旨文書で報告致します。問題があると考えられる場合は、さらに相手方医療機関との交渉等の手続きについてご説明致します。
交渉等を選択されるかどうかは、説明の上で、依頼者の方が決めて頂くようになります。
一般的に、弁護士に対する相談をしても、必ず依頼しなければならないという拘束力はありませんので、疑問をお持ちの方は一度ご相談されることをお勧めします。
勝訴判決報告
胃カメラ検査中に、前投薬であるキシロカインによるショックで死亡した患者の遺族が医療機関を訴えた訴訟で、2005年12月15日、福岡高裁は、1審の原告敗訴判決を取り消し、医療機関の責任を認める判決を下しました。
1審は、患者の死因を脳幹部梗塞も疑われるとした上で、医療機関の過失を否定しましたが、高裁は、死因を正しくキシロカインショックと認定し、投薬の前後に十分な問診・検査を行わなかった責任と、十分な救命処置を行わなかった責任を認め、逆転勝訴の判断を下しました。
この判決は、稀ではあっても実際に起こりうるキシロカインショックの病態を正確に捉え、的確に判断したものです。
また、救命措置の適否については、本来あるべき記録がないこと、特に、心電図記録については、「そもそもなかった」「あったけど紛失した」という不合理な弁解を繰り返して提出をしないという不自然な対応に対し、客観的証拠を提出できない医療機関に立証責任を負わせました。
密室の出来事で、何も情報の得られない患者・遺族に、ことさらに詳細な責任原因の立証を求め、責任がないからではなく、証拠が隠されたから裁判に負けてしまうという不公正を認めない画期的な判決で、他の医療過誤訴訟にも大きく影響を与えるものです。
(2005.12.16西日本新聞朝刊(福岡都市版)に、私のコメントが掲載されています。)
具体的な解決事例
担当して解決した事件の中から、一部ご紹介いたします。
左腕への注射による神経損傷(RSD)事件
2015年5月13日に示談した事件です。
福岡市にお住まいの20代の女性です。
被害者は、2006年に、高校生の時に後行の球技大会で熱中症になり、福岡県内の総合病院に救急搬送されました。
左上腕筋肉に注射を受けた際、それまでに経験したことのない強い痛みを感じ、「痛い」と叫びましたが、担当の看護師は、注射を中止することなく「我慢してね」と言ってそのまま継続されました。
左上腕が腫れ、感覚がないけれども痛くなり、左手指がしびれ、感覚がなくなりました。痛みで眠ることもできない状態でした。
左腋窩神経障害と診断され、1ヶ月ほど入院し、その後は通院を続け、2012年10月3日に症状固定となりました。
左肩関節拘縮、左手指屈曲拘縮などの後遺障害を負いました。
2013年3月に、医療事故の調査・交渉のご依頼を受け、同年6月に相手方病院に請求書を出しました。
筋肉注射に際しては、神経損傷を起こさないよう、細心の注意を払うべき義務が看護師にあり、注射の際に患者が強い痛みを訴えた場合、それが神経損傷に起因する可能性があることを考慮して、直ちに中止し、経過観察を行うべきであることを責任原因としました。
相手方医療機関の代理人(弁護士)から、後遺障害に関連する資料の追加を求められました。作成医療機関に限定があったため、提出に若干の時間がかかりましたが、後遺障害12級該当を前提とし、1400万強を支払っていただく内容での示談に至りました。
2007年にご両親が最初の相談に来られましたが、その時点では、被害者はまだ未成年でした。
治療費の実費は返してもらったけれども、それ以外は見舞金20万円の支払いで終わりにしてほしいと言われ、納得できないというご相談でした。
ご本人がまだお若いことなどから、その時点では、可能な限り事故前の状態に戻るよう、治療に専念して下さいというアドバイスをしました。
医療被害を受けた被害者でしたが、その後の治療やリハビリを受けた結果、医療に携わる職に就かれました。
後遺障害との関係での不自由があると思いますが、医療に絶望することなく、前向きに関わられる姿がすばらしいと思います。
無理をしないでがんばっていかれるようお祈りしております。
腹腔鏡下胆のう摘出術による胆管狭窄事件
2014年4月25日に和解した事件です。翌日の朝日新聞朝刊、西日本新聞朝刊で報道されました。
福岡市にお住まいの58歳の女性です。
被害者は、2008年10月に胆石のため、福岡県内の総合病院で腹腔鏡下胆のう摘出術を受けました。
ところが、手術後、胆管狭窄(胆汁の通り道が狭くなる状態)が起こり、3ヶ月おきにステント(狭くなった胆管を広げるために挿入する管)を入れ替え続ける必要が起こり、胆管炎にも悩まされるようになってしまいました。
2011年4月に医療問題研究会の相談に見え、私が担当しました。
被害者は、身体的な不自由による苦痛に加え、どうしてこういう状態になったのかと説明を求めているうちに、病院からは半ばクレーマーのように捉えられ、なおいっそう納得のいかない状態になりました。
持参されたカルテには、「操作中総胆管を胆嚢頸部と誤認していて上記*(カルテ上の図に書き込まれたマークを指す)剥離操作中総胆管一部損傷 胆汁の漏出少量あり」と書かれていました。
誤認という、本来避けられるべきことが起こっていたことは率直に記録されていると思いました。
他方で、この手術ではDVD記録が残されており、これを解明する必要がありました。
専門医の協力を得て問題点を特定し、相手方病院への聴き取りも踏まえ、12月に病院に請求書を送りました。
2012年4月に得られた回答は満足のいくものではなかったため、7月に福岡地方裁判所に提訴しました。
裁判では、DVDの画像をもとに、どの部分の手術操作が、どのように問題なのかが争点となりました。
原告は、腹腔鏡下胆のう摘出術の一般的な手法とDVD画像との違いについて、被告に説明を求めました。また、それと合わせて、この手術が極めて安全な手術とされ、手術中に胆管損傷を起こすケースは全体の0.56%しかなく、手術後に胆管狭窄を起こすほど胆管損傷が高度な例は全体の0.04%(2万5174件中の9件:平成20年、日本内視鏡外科学会アンケート)しかなかったことを示しました。そして、術前、術中の検査で、誤認は確実に回避できるはずであり、にもかかわらずやむを得なかったというのであれば、むしろ病院が例外的な事情を証明すべきであると主張しました。
その後、裁判所による争点整理がなされ、原告が執刀医と、手術後の説明を担当していた医師の尋問を申請して、尋問の準備に入ったときに、裁判所から和解の提案がなされました。
原告は、病院に責任があることを前提とした和解でなければ受け入れられないと答えました。
2014年3月には、胆道系の解剖学的位置関係が不明瞭な場合には手術中に検査を行うべきだった点について責任が認められる可能性が高いという前提で和解案が提出されました。
原告、被告ともこの提案を受け入れることとし、1300万円の支払いがなされる和解が成立しました。
被害者の女性は、身体を傷つけられた苦痛以上に、当然の疑問に対して誠実に非を認めない医療側の態度に、人としての尊厳を損なわれたという被害を感じておられたのではないかと思います。最初の相談の時から、理解あるご家族がサポートされ続けました。
被害者ご自身も、寄り添い続けたご家族も、和解案の提示に際して裁判官による口頭での説明で、「医療機関側に落ち度が認められる可能性が大きい」との暫定的な心証が述べられたときに、それまで張り詰めていた表情が軽くなられたように感じました。
その後は、むしろ笑顔も見え、おふたりとも明るい表情になったように思います。
被害者ご自身とご家族の思いが裁判官に伝わったという達成感をもつことができました。
本件では、原告は医師の意見書もなく、鑑定も申請せず、医師の尋問もないまま勝訴的和解ができました。
インプラントによる神経損傷事件
2012年12月に最終の打ち合わせをした事案です。
福岡県筑紫野市にお住まいの60代の女性です。
被害者は、2009年12月に、近くの歯科を受診し、右下5,6部のインプラントを強く勧められました。手術に伴う合併症の説明はありませんでした。
まもなく、インプラント手術を受けましたが、術後、右口唇部、下顎部に麻痺を生じ、「右オトガイ神経知覚鈍麻」と診断されました。
その後、インプラントの摘出術を受け、長期間治療を受けましたが、右口唇部、下顎部の麻痺はよくなりません。
2011年8月に医療問題研究会の相談に見え、私が担当しました。
インプラント術は、最近よく行われていますが、手術前の検査が十分でないと、一定割合で、神経損傷が生じると指摘されています。
本件では、パノラマエックス線撮影しか実施されておらず、CT撮影がなされていません。顎骨の三次元形態の把握、骨量、骨形態の把握が不十分と考えられました。
相手方歯科への聴き取りを経て、2012年1月に請求書を送付しました。
相手方に付いた弁護士から後医のカルテの提出を要請されたためにこれを取得して提出したところ、7月に具体的な対案を受け取りました。
ご本人と打ち合わせたところ、早期の解決を希望されたため、9月に再度連絡文を送付しました。10月中に示談の合意がなされ、11月に示談書を送付しました。
示談の内容は、既払い額のほか、230万円を支払うという内容でした。
神経損傷は、つらい症状が長く続いてしまい、精神的に参ってしまうことがよくあります。最後の打ち合わせの時に、被害者の女性は、「こんなふうになるとは思ってもみなかった。もとの体に戻してほしいという気持ちでいっぱいだ。でも、そんなことを言っても今さらどうにもならない。今後、私のような人が出ないように、不十分なインプラントはしないでほしいし、被害を受けた人がいたら、泣き寝入りしないでいいように、弁護士に相談してほしい。」とおっしゃっていました。
出血性ショック死亡事件
2012年10月に最終の打ち合わせをした事案です。
糟屋郡にお住まいの、60代の女性で、事故にあわれたのは、この方のお母さん(当時80代)です。
被害者は、2011年5月に大腿骨を骨折し、福岡県内の総合病院でいったん手術を受けました。そして、7月に再度手術(抜釘術、人工骨頭挿入術)を受けました。
13:15に手術室に入り、15:45に手術室から病室に戻ってきました。医師から、輸血についての家族の同意書が取られています。しかし、輸血用の血液は病院内になく、16:10に発注はされましたが、なかなか届きませんでした。
血液が到着する21:39より前の、20:30には、意識不明(JCSⅢ-300)、舌根沈下の状態に至っており、蘇生術が施されましたが、お亡くなりになりました。
2011年10月に、医療問題研究会に相談に来られ、私が担当しました。
相談時の印象として、一般的に出血性ショックで亡くなってしまうような手術ではないと思いました。持参されたカルテを見ると、ワーファリン投与中で、術中出血も相当量あるのに、バイタルの観察も十分になされておらず、緊張感が感じられませんでした。
10月中に調査事件として依頼を受け、検討しました。貧血傾向であったのに、手術直前に血液検査を行っていない点や、ワーファリン投与中の高齢者への手術なのに、輸血用の血液を準備しないで手術に臨んだことや、術中の相当量の出血量にもかかわらず、十分な経過観察がなく、緊急で血液を配達してもらう指示もない点なども問題となりました。2012年2月に相手方病院に聞き取りに行きましたが、合理的な説明は得られませんでした。
3月に、相手方病院あてに請求書を送付しました。
8月に、相手方病院が陳謝し、解決金として約2350万円を支払う内容の示談が成立しました。
医療事故は、いったん起こってしまうと、取り返しのつかない被害となります。依頼者の方は、二度とこのような事故を起こさないように病院に真剣に反省してほしいというお気持ちでした。
依頼者によると、示談成立後、相手方病院の方がお参りに来られたそうです。
示談書で謝罪が得られたこと、お参りに来られて謝罪されたことで少し救われた思いだ、とおっしゃいました。
それでも、弁護士への相談にたどり着くまでに、どこに相談すればよいのかわからずいろいろなところを回って大変だったとおっしゃっいました。お名前等が特定されない前提で、ほかに同じような状況で困っていらっしゃる方のために広報してよいですとおっしゃったので、このような形でご報告することとしました。
予想もしていなかった結果になるなど、納得がいかない医療被害にあわれた方は、一度弁護士にご相談ください。
大動脈解離死亡事件
2012年3月14日に、福岡地方裁判所で和解が成立した事案です。翌日の新聞等で報道されました。
2007年1月に、福岡市内に住んでおられた70代の男性が、胸が苦しくて目が覚めたといって午前6時40分に、近くの大学病院の救急外来を受診されました。血液検査や心電図検査、胸部レントゲン検査等では異常がないとして、原因探索のために午前10時過ぎに緊急入院となりました。
午後0時過ぎに、狭心症又は心筋梗塞の除外診断として冠動脈造影検査が施行されましたが、持続する胸痛を説明できる異常は見つかりませんでした。
病院は、翌日胃カメラ検査を予定としてそのままにしました。
午後4時40分には、嘔吐し、血圧も80/47まで低下しました。
そして、翌日午前1時頃、心肺停止状態で発見され、亡くなりました。
死因は、急性大動脈解離(DebakeyⅠ型)の外膜破綻による心タンポナーデでした。
2007年9月に、医療問題研究会の相談で私が担当しました。
2008年5月に、医療事故調査の依頼を受け、自分たちで調査をした上、11月に、相手方病院に聴き取りを行いました。
2009年6月に、法的責任を前提とした請求書を送付しましたが、12月に、責任はないとの回答がありました。
2010年5月に提訴しました。
私は、救急外来を受診するような胸痛、胸部絞厄感を自覚している患者に対しては、教科書的文献で指摘されているように、致命的疾患である①急性心筋梗塞、②大動脈解離、③肺梗塞の除外診断が必須であることを訴えました。
そして、本件では、病院も①の除外診断を実施しているように、ただならぬ胸痛だったこと、①が除外された時点で、②の疑いはさらに濃くなっているのであるから、必ず除外診断をすべきだったのに、これを怠って②で死亡させたのは、教科書的な典型的な失敗であると訴えました。
病院側は、大動脈解離の場合には、激しい胸痛や背部痛が伴うはずだが、本件ではなかったから疑うまではなかった、そもそも胸痛が持続していなかった、ニトロペンに反応があって攣縮性狭心症を疑ったなどと主張し、検査をする義務はなかったと主張しました。
当方では、医師など専門家の協力者による意見書等は全くありませんでしたが、医学文献にもとづく主張を展開し、相手方大学病院の医師(当時の主治医を指導していた医師)を反対尋問し、胸痛が重大なものであり、かつ持続していて狭心症の疑いは低かったから、検査すべきであったことを明らかにしました。
和解内容は、約3700万円の請求に対して、遺族に対して総額3000万円を支払うこと、「被告は、原告らに対し、本件事故の発生と結果について陳謝し、同種事故の再発防止に努める。」ことなどを内容とするものでした。
大動脈解離については、ガイドラインでも、「三次救急病院へ搬送されてくる割合が約3分の2ということは、多くの例の初期診断はもよりの救急病院においてなされていることを示しており、救急診療科、一般内科医、脳神経専門医、消化器専門医、循環器専門医など各自が疑いを持って診断に当たることが何より重要である。」とされています。
この大学病院は、三次救急病院(地域で最も高度な責任を持つ救急医療機関。2012年1月当時で福岡県内に8病院、福岡市内には3病院しか存在しない。)なので、まちなかにある病院から大動脈解離の疑いがある患者が搬送されてくる、救急病院における「最後のセイフティーネット」のはずです。
にもかかわらず、自分の病院の救急外来を受診した患者の大動脈解離を見落とし、それで急死させると言うことはあってはならないことです。
本来、責任を争うことなく、示談で解決されるべきでしたし、二度とこのような事故をくり返さないと言うことが最高度の救急医療機関の公的責任として必要です。
私の目には、大学病院特有の、専門疾患への強いバイアス(担当科は虚血性心疾患を専門としている)、血管外科との連携のなさ(「経食道心エコーについては詳しくは知らないんですけども」)などの問題が見えました。
二度と同じような被害者を出さないよう、胸痛患者に対する鑑別のスキルアップ及び他科との連携が図られるべきだと思いました。