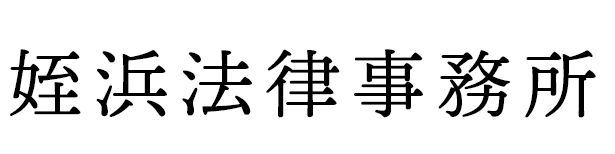* 分娩監視(経時的な波形の確認)がされていない出産事件
2024年9月に示談した事件です。
福岡市にお住まいの30代の女性です。
初産で、産婦人科に通院されていました。出産前のカルテには、検査で確認された「首に巻絡2回(きつく)」との所見がありました。
2021年3月のある夜に陣痛がきて、入院されました。翌日の深夜には、胎児心拍数陣痛図で軽度変動一過性徐脈、早発一過性徐脈が認められ、胎児心拍数波形分類はレベル2~3で推移していました。早朝に助産師が院長へ連絡し、頭位経膣分娩に至りました。
しかし、新生児のアプガースコアは1/2点で、新生児仮死の状態でした。
総合病院の小児科医師が来院し、救命措置を行い、転院となり、重症新生児仮死、低酸素性虚血性脳症等と診断されました。今後も、自発的運動が出るのは困難と考えられています。
分娩の経過を見ていて驚いたのは、未明の時刻以降、助産師が胎児心拍数陣痛図を装着しているものの、波形の記録(経時的なプリントアウト)を行っていなかったことでした。
産婦人科診療ガイドラインを引用するまでもなく、分娩時においては、胎児心拍数陣痛図を監視すること、つまり、胎児が健やかであるかどうか、健康を損なう状態に至っていないかを知るために波形を見て、継続的に安全を確認していくこと、危険が生じたら医師に報告し帝王切開等の選択肢を確保する必要があることは常識です。
特に、胎児には臍帯が首に2回巻絡していることが事前に分かっていたので、より慎重な対応が求められており、波形の記録を省略するとは信じられない対応でした。
胎児の健康状態に対する慎重な観察と評価、対応がなされれば、新生児仮死に至ることは十分に避けられました。
産科医療補償制度の申請手続きが完了した後、2023年夏に産婦人科に聴取にうかがい、その10月に請求書を送付しました。
2024年8月に、産科医療補償制度から既に受領した額を含めると、総額1億4850万円となる額での示談提案を受け、9月に示談に至りました。
産科医療補償制度が開始した後での産婦人科の事件は初めて担当しました。この制度には産婦人科医の協力が不可欠なため、調査はしばらく待機する形となり、後遺障害の調査を進めました。産科医療補償制度では、原因分析で、専門性に基づく誠実な報告がなされ、感銘を受けました。
私は、過去に危険な波形の見落としの事故(有責で訴訟上の和解)は経験したことがありますが、そもそも、「目の前を全く見ない約80分の脇見運転」のような、波形を全くみない分娩は想像もしていませんでした。
かけがえのない出産に対して、産婦人科には、一つの症例に過ぎないという意識がなかったでしょうか。本人だけでなく、両親やそのほかの家族も含めたたくさんのひとの人生を変えてしまうような重大な結果と比較して、助産師の方の緊張感のなさには言葉が見つかりません。医療機関全体で、きちんと安全な体制が確保されるべきものと思いました。